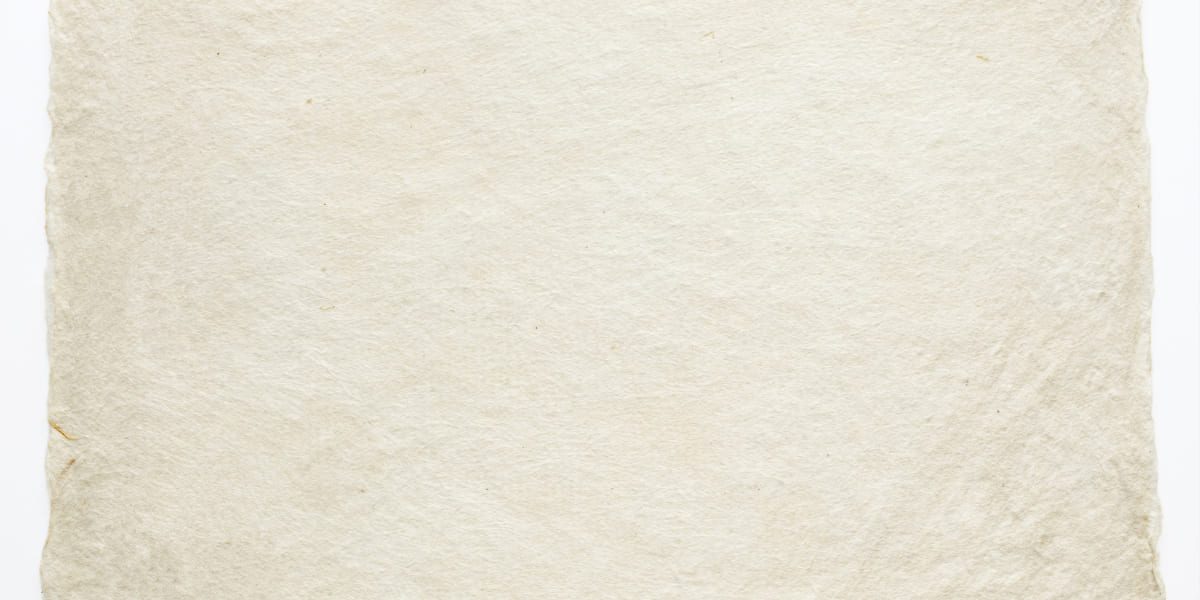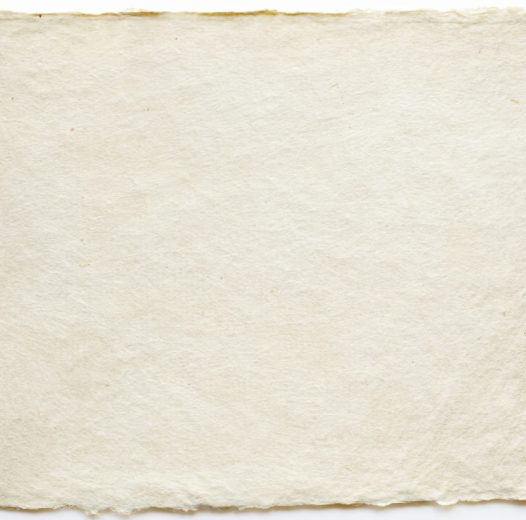日本の伝統文化を象徴する「和紙」は、自然素材と職人の技から生まれる繊細で奥深い美しさを持つ特別な紙です。その魅力を紐解いていきます。
そもそも和紙とは
和紙とは、日本で独自に発展してきた紙のことを指します。もともとは中国から伝わった製紙技術が、日本の風土や文化の中で改良され、独特の技法や素材が生まれました。「和紙」という言葉自体は、明治時代に洋紙と区別するために使われるようになったものです。
和紙の特徴のひとつは、その原料です。楮(こうぞ)、雁皮(がんぴ)、三椏(みつまた)など、日本に自生する植物の繊維が使われており、これらは洋紙の原料である木材パルプよりも繊維が長く、絡み合いやすいため、薄くても破れにくいという性質を持ちます。また、伝統的な製法である「手漉き(てすき)」では、繊維が均等に絡むように職人が水中で紙料をすくい、ゆらしながら丁寧に漉いていきます。
2014年には、島根県の石州半紙、岐阜県の本美濃紙、埼玉県の細川紙という3種の手漉き和紙技術がユネスコの無形文化遺産に登録され、世界からもその価値が認められるようになりました。長い歴史と伝統に育まれてきた和紙は、まさに日本が誇る文化のひとつです。
和紙の作り方
和紙の製造には、長い時間と手間がかかります。まずは、原料となる楮などの植物の皮を剥ぎ、アク抜きをしてから柔らかくなるまで煮ます。さらに不純物を取り除いた後、繊維を棒で叩いて細かくほぐしていきます。この作業を「叩解(こうかい)」といい、紙の質感や強度に大きく影響します。
次に「紙料」と呼ばれる繊維のもとを水に溶かし、トロロアオイなどの植物の根から抽出した「ネリ」と呼ばれる粘り気のある液を加えます。ネリによって繊維が水中で均等に分散しやすくなり、美しい紙を作る助けとなります。
紙を漉く工程では、「簀桁(すけた)」という道具を用いて、水中から紙料をすくい上げます。このとき、前後左右にゆっくりと揺り動かす「流し漉き(ながしずき)」という技法が使われます。この動きによって繊維が絡み合い、丈夫で均質な紙ができあがるのです。
漉いたあとは、一枚ずつ板に貼りつけて天日で乾燥させます。この全工程は手作業が中心で、職人の技術と感覚が何よりも重要です。自然の素材と人の手が生み出す和紙には、機械では再現できない温かみと風合いがあります。
新しい和紙の活用方法
伝統的な素材である和紙ですが、現代の暮らしの中でもその魅力は再発見されています。たとえば、ファッションの分野では、和紙繊維を用いたシャツやデニムが登場しています。和紙は通気性や吸湿性に優れており、肌触りもやさしいため、衣類の素材としても注目されています。
また、インテリアでは「和紙畳」や「和紙照明」が人気を集めています。特に和紙畳は、細かくこより状にした和紙を編み込んで作られ、い草よりも耐久性が高く、デザイン性にも富んでいます。和の雰囲気を演出しながら、現代的な住空間にもなじむ素材として活用されています。
さらに、博物館や図書館では、古文書の修復にも和紙が欠かせません。薄くても丈夫な和紙は、数百年前の紙の上に貼っても違和感が少なく、保存性にも優れているためです。
そして、近年では、地域によっては子どもたちが卒業証書のために和紙を漉くという取り組みも行われています。伝統を体験しながら、暮らしの中に文化を取り入れるこうした活動は、和紙の未来をつなぐ希望でもあります。